- TOP
- 共済組合のしくみ
- 掛金(保険料)と負担金
- 掛金(保険料)の率と負担金の率
掛金(保険料)の率と負担金の率
令和7年4月からの掛金(保険料)・負担金率等
短期・福祉・その他
※この表は右にスクロールできます。
| 種別・年齢 | 短期 (介護掛金・介護負担金は40-64歳の組合員のみ対象) |
福祉 | 事務費負担金(月額・組合員一人あたり) (注3) |
子ども・子育て拠出金 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 掛金 | 負担金 (注1) |
介護掛金 | 介護負担金 | 調整負担金 | 掛金 | 負担金 | ||||
| 70歳未満組合員 | 一般職 特別職 市町村長組合員 特定消防組合員 |
50.0 | 50.87 (0.87) |
8.10 | 8.10 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 889円 | - |
| 労組専従者 | 50.0 | 50.87 (0.87) |
8.10 | 8.10 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 889円 | 3.6 | |
| 在職派遣 | 50.0 | 50.87 (0.87) |
8.10 | 8.10 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 889円 | 3.6 | |
| 地方独立行政 法人職員 |
50.0 | 50.0 | 8.10 | 8.10 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 889円 | 3.6 | |
| 短期組合員 | 50.0 | 50.87 (0.87) |
8.10 | 8.10 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 415円 | - | |
| 船員短期組合員 | 48.37 | 52.50 (0.87) |
8.10 | 8.10 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 415円 | - | |
| 船員一般組合員 | 48.37 | 52.50 (0.87) |
8.10 | 8.10 | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 889円 | - | |
| 70歳以上 75歳未満組合員 |
70歳以上75歳未満 一般組合員 |
50.0 | 50.87 (0.87) |
- | - | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 889円 | - |
| 70歳以上75歳未満 短期組合員 |
50.0 | 50.87 (0.87) |
- | - | 0.1 | 2.0 | 2.0 | 415円 | - | |
| 75歳以上組合員 | 長期組合員 市町村長長期 組合員 |
2.52 | 3.39 (0.87) |
- | - | - | 2.0 | 2.0 | 889円 | - |
| 後期高齢者等 短期組合員 |
2.52 | 3.39 (0.87) |
- | - | - | 2.0 | 2.0 | 415円 | - | |
| 継続長期組合員 | - | - | - | - | - | - | - | 889円 | 3.6 | |
| 任意継続組合員(注2) | 104.0 | - | 16.20 | - | - | - | - | - | - | |
| (注1) | 短期負担金率中の( )は、育児・介護休業手当金・育児休業支援・育児時短勤務手当金に係る公的負担金率を示しています。なお、地方独立行政法人は、公的負担金の対象外です。 |
|---|---|
| (注2) | 任意継続組合員の掛金率には、福祉事業分の財源率(4.0‰)を含みます。 |
| (注3) | 任意継続組合員を除く全ての組合員が対象です。ただし、労組専従者については、派遣元の地方公共団体の負担となります。 |
長期
※この表は右にスクロールできます。
| 種別・年齢 | 厚生年金保険料 | 基礎年金拠出金 | 退職等年金給付 | 公務等障害・ 遺族年金負担金 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 組合員 保険料 |
負担金 | 公的負担金 | 掛金 | 負担金 | 負担金 | ||
| 70歳未満組合員 | 一般職 特別職 市町村長組合員 特定消防組合員 |
91.5 | 91.5 | 41.5 | 7.5 | 7.5 | 0.0939 |
| 労組専従者 | 91.5 | 91.5 | 41.5 | 7.5 | 7.5 | - | |
| 在職派遣 | 91.5 | 91.5 | 41.5 | 7.5 | 7.5 | 0.0939 | |
| 地方独立行政法人職員 | 91.5 | 91.5 | 41.5 | 7.5 | 7.5 | 0.0939 | |
| 短期組合員 | - | - | - | - | - | - | |
| 船員短期組合員 | - | - | - | - | - | - | |
| 船員一般組合員 | 91.5 | 91.5 | 41.5 | 7.5 | 7.5 | 0.0939 | |
| 70歳以上 75歳未満組合員 |
70歳以上75歳未満 一般組合員 |
- | - | - | 7.5 | 7.5 | 0.0939 |
| 70歳以上75歳未満 短期組合員 |
- | - | - | - | - | - | |
| 75歳以上組合員 | 長期組合員 市町村長長期組合員 |
- | - | - | 7.5 | 7.5 | 0.0939 |
| 後期高齢者等 短期組合員 |
- | - | - | - | - | - | |
| 継続長期組合員 | 91.5 | 91.5 | 41.5 | 7.5 | 7.5 | 0.0939 | |
| 追加費用 | 標準率10.1‰(厚生年金9.0‰、経過的長期1.1‰) |
||||||
| 標準率以外の所属所の率 岡山市 12.6‰(厚生年金11.1‰、経過的長期1.5‰) 倉敷市 11.3‰(厚生年金10.0‰、経過的長期1.3‰) 津山市 10.7‰(厚生年金9.5‰、経過的長期1.2‰) 玉野市 11.8‰(厚生年金10.5‰、経過的長期1.3‰) 笠岡市 10.7‰(厚生年金9.5‰、経過的長期1.2‰) 備南水道 10.9‰(厚生年金9.7‰、経過的長期1.2‰) |
|||||||
| (注1) | 厚生年金の保険料・負担金及び基礎年金拠出金に係る公的負担金は、70歳以上の組合員からは徴収しません。 |
|---|---|
| (注2) | 短期組合員には長期給付が適用されないため、長期給付に係る掛金(保険料)と負担金の負担はありません。 |
標準報酬とは
標準報酬とは、共済組合に納める掛金(保険料)や負担金、共済組合から支給される給付金等の額等を計算する際の基礎となる額です。
組合員が受ける報酬に基づき、「標準報酬月額」及び「標準期末手当等額」の2種類が決定されます。
標準報酬月額
組合員が受ける、毎月の報酬(基本給+諸手当)の合計額を、「標準報酬等級表」に当てはめて算定したもので、大幅な報酬の増減がない限り、原則1年間は変わりません。
なお、掛金・負担金を計算する際は、下記のとおり事業ごとに上限額が設けられています。
| 短期・福祉・介護 | 厚生年金・退職等年金・経過的長期 |
|---|---|
| 1,390,000円 | 650,000円 |
標準報酬月額の決定
決定方法については、原則として次の5種類です。
資格取得時決定
新たに組合員の資格を取得したときはその資格を取得した日の現在の報酬の額(基本給+諸手当)により、標準報酬月額を決定します。資格取得時決定で決定された標準報酬月額は、資格を取得した日からその年の8月31日(6月1日から12月31日までの間に資格を取得した方は、翌年の8月31日)まで適用されます。
定時決定
毎年7月1日現在の全組合員を対象に、毎年1回4月から6月までの報酬の平均額を基に標準報酬月額を決定します。これをその年の9月から翌年の8月までの各月の標準報酬月額とします。
ただし、以下の組合員は定時決定の対象外です。
- 6月1日から7月1日までの間に資格を取得した組合員
- 7月から9月までのいずれかの月から随時決定、育児休業または産前産後休業終了時改定を行う組合員
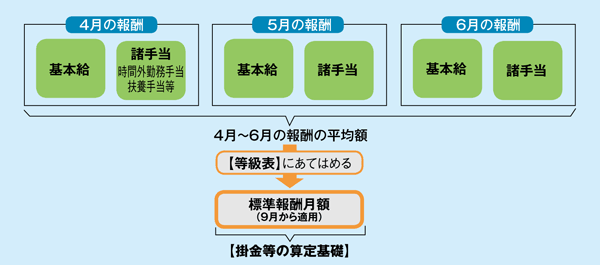
通常の算定結果が著しく不当となる場合の特例─年間報酬の平均で算定する場合─
定時決定は、原則として、4月〜6月の3か月間に受けた報酬月額の平均により、標準報酬の月額を決めますが、季節的な繁忙期がある等の業務の性質上、通常の方法によって報酬月額の算定を行うことが著しく不当であると認められる場合については、年間報酬の平均で算定することができます。
<年間報酬の平均で算定することが認められる基準> ※ 次の3つの要件を全て満たす必要があります。
| ① | 「当年の4月〜6月の3か月間に受けた報酬月額の平均額により算定した標準報酬の月額」と「過去1年(前年7月〜当年6月まで)の年間報酬の平均額により算定した標準報酬の月額」との間に、2等級以上の差が生じること |
|---|---|
| ② | この2等級以上の差が業務の性質上、例年発生することが見込まれること |
| ③ | 年間報酬の平均で算定することについて組合員が同意していること |
<年間平均の算定方法>
前年7月~6月の報酬(基本給+諸手当)の平均額を、標準報酬等級表に当てはめます。
<産前産後休業時の特例>
4月から6月の間に産前産後休業を取得する組合員について以下の条件を満たせば年間平均による定時決定が可能です。
| ① | 4月から6月の間に産前産後休業を取得していること(条例による予定日56日前からの休業) |
|---|---|
| ② | 通常の算定方法による標準報酬月額が「休業開始以前の直近12か月の標準報酬月額の平均額を等級表に当てはめた標準報酬月額」より2等級以上「下がる」こと |
| ③ | 該当する組合員から、年間平均による定時決定をする旨の申出をすること |
| ※ | 本特例は4月~6月の間に産前産後休業を取得することでその後の育児休業手当金の算定基礎となる標準報酬月額が下がることに対する救済措置です。そのため、当組合からの育児休業手当金が発生しない組合員(独立行政法人職員など) については本特例の対象外となります。 |
|---|
<必要な書類> ※ 所定の様式があります。詳しくは所属所の共済事務担当者におたずねください。
- 該当する所属所からの「基礎届」
- 該当する組合員の申出書
<必要な書類> ※ 所定の様式があります。詳しくは所属所の共済事務担当者におたずねください。
- 該当する所属所からの申立書
- 該当する組合員の同意書
随時改定
昇給などにより報酬に著しい変動があり、その変動した月から継続した3か月間の報酬の平均額を基に、標準報酬の等級を算定して2等級以上の差があった場合に、その変動があった月から数えて4か月目に標準報酬月額を改定します。随時改定された標準報酬月額は次の定時決定まで適用されます。
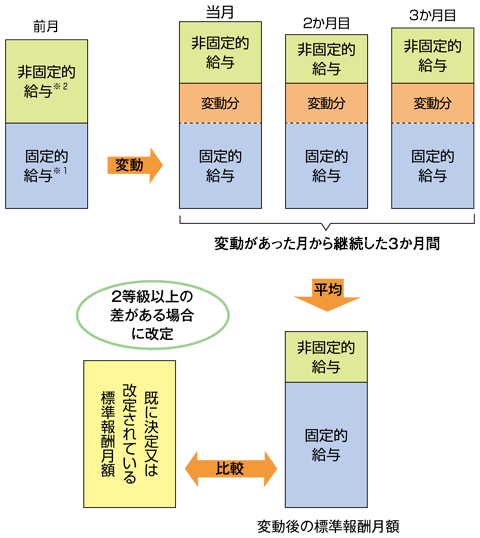
| ※1 | 基本給(給料表の給料月額)・扶養手当・へき地手当・住居手当・通勤手当など |
|---|---|
| ※2 | 特殊勤務手当・時間外勤務手当・休日勤務手当・夜間勤務手当・寒冷地手当など |
<年間平均による随時改定>
随時改定の算定が、組合員本人にとって著しく不利益になる場合であり、以下の条件を満たす場合に行うことができる算定方法です。
| ① | 通常の随時改定による算定と、年間平均による算定の差が2等級以上であること |
|---|---|
| ② | その差が業務上の性質上、例年発生することが見込まれること |
| ③ | 年間報酬の平均で算定することについて組合員が同意していること |
年間平均による算定を行う際に使用する報酬は、次の①②の合計額を標準報酬等級表に当てはめた額です。
| ① | 変動月以後の継続した3か月の固定的給与の平均額 |
|---|---|
| ② | 変動月前の継続した9か月および変動月以後の継続した3か月の非固定的給与の平均額 |
年間平均による随時改定を行う場合は改定前と1等級でも差があれば改定できます。差がなかった場合や下回った場合は「保険者算定の結果、随時改定を行わない」ことができますが、その場合も申立書と同意書の提出が必要になります。
産前産後休業終了時改定
産前産後休業を終了した組合員が産前産後休業終了日においてその産前産後休業に係る子を養育する場合、組合に申出をした時は産前産後休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。産前産後休業終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、産前産後休業終了日の翌日に育児休業等を開始している場合は、対象外となります。
育児休業等終了時改定
育児休業等を終了した組合員が育児休業終了日において、その育児休業に係る3歳に満たない子を養育する場合、組合に申出をした時は育児休業終了日の翌日が属する月以後3か月に受けた報酬の平均額を基に標準報酬を改定します。育児休業等終了時改定により改定された標準報酬の月額は次の定時決定まで適用されます。ただし、育児休業等終了日の翌日に産前産後休業を開始している場合は、対象外となります。
3歳未満の子を養育している期間の特例(養育特例)⇒手続きについてはこちら
3歳未満の子を養育している又は養育していた組合員又は組合員であった者が組合に申出をしたときは、その子を養育することとなった日の属する月から、その子が3歳に達した日等の翌日の属する月の前月までの各月のうち、標準報酬月額がその子を養育することとなった日の属する月の前月の標準報酬月額を下回る月については、従前の標準報酬月額で年金額が計算されます。
なお、この特例は、将来の厚生年金及び年金払い退職給付の額が低くなることを避けるために行われるものであることから、短期給付の算定の基礎となる標準報酬については、適用されません。
育児休業等終了時改定及び養育特例(注)を申し出た場合のイメージ
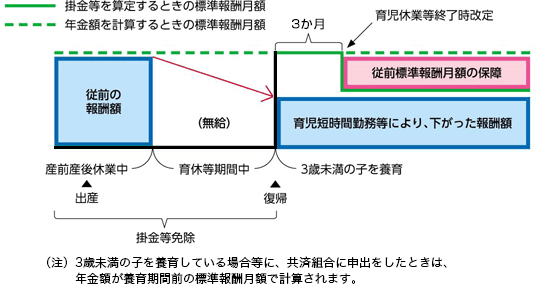
標準期末手当等額
組合員が受ける、期末手当等(期末手当・勤勉手当・任期付研究員業績手当・特定任期付職員業績手当)の支給額から千円未満を切り捨てたものです。
期末手当等が支給されるたびに決定するもので、標準報酬月額のように等級表に当てはめることはありません。
なお、掛金・負担金を計算する際は、標準報酬月額と同様に、事業ごとに上限額が設けられています。
| 短期・福祉・介護 | 厚生年金・退職等年金・経過的長期 |
|---|---|
| 5,730,000円 (年度単位の上限) |
1,500,000円 (支給期ごとの上限) |
不服の申し立て
組合員の権利を守るために、組合員の資格、共済組合からの給付、掛金等の徴収、被保険者(組合員)期間の確認などについて不服がある者は、全国市町村職員共済組合連合会に置かれている審査会に対し、審査請求をすることができます。この審査請求は、給付に関する決定などを知った日から、正当な理由がある場合を除き、3月以内にしなければなりません。
なお、この審査請求は、訴訟による権利救済を妨げるものではありません。また、この審査会の裁定に更に不服があるときは訴訟を提起することもできます。
任意継続組合員の掛金
任意継続組合員について
任意継続組合員の掛金について
掛金
医療・福祉の給付に係る「短期掛金」と、介護保険に係る「介護掛金」(40歳以上65歳未満の方が対象)との合算額となります。
(1)納付期間
任意継続組合員の資格を取得した日の属する月から、その資格を喪失した日の属する月の前月までの各月。
(例1) 4月1日に任意継続組合員の資格取得、翌年2月10日に他の健康保険の資格を取得した場合

| ※ | 資格喪失月(2月)分の掛金は、納付の必要はありません。すでに納付いただいている場合は、後日共済組合から還付いたします。 |
|---|
(例2) 4月1日に任意継続組合員の資格取得、翌年1月4日から家族の被扶養者になったため資格喪失の申し出を行い、1月17日に申出が受理された場合

| ※ | この場合、被扶養者の資格取得日が1月の中途であったとしても、任意継続組合員の掛金は1月分まで納付いただく必要があります(国民健康保険に加入した場合も、同様の取り扱いとなります)。 |
|---|
(例3) 4月1日に任意継続組合員の資格取得、同月の25日に他の健康保険の資格を取得した場合

| ※ | 任意継続組合員の資格を取得した日と資格を喪失した日が同月内の場合は、その月の掛金を納付していただく必要があります。 |
|---|
(2) 計算方法
| ※ | アまたはイの、いずれか低い額を使用します。 (円未満切捨て) |
|---|
| ア | 退職時の標準報酬月額(短期) | × |
掛金率 (参考)令和7年度 短期:104/1000 介護:16.2/1000 |
| イ | 共済組合が定款で定める額 380,000円 |
(参考) 任意継続掛金一覧表
(3) 払込方法
【資格取得時(1年目)】
「任意継続組合員資格取得申出書」を提出する際に、あらかじめ次の3通りの方法の中から、いずれかを選択していただきます。
| ア) | 月払い(各月毎に払い込む方法) |
|---|---|
| イ) | 半年前納(半年分ずつ、年2回払い込む方法。前納による割引あり。) |
| ウ) | 1年前納(1年分をまとめて払い込む方法。前納による割引あり。) |
| ※ | 年度の途中で払込方法を変更することは、原則としてできません。 |
後日、組合員証と一緒に「払込用紙」を送付しますので、共済組合が指定する期日までに払い込んでください。払込金融機関は「中国銀行」となります(他の金融機関での払込も可能ですが、振込手数料がかかる場合があります。)
【継続加入時(2年目)】
3月上旬頃、2年目の継続に関するご案内文書をご自宅に送付しますので、継続を希望する場合は、同封している「払込用紙」を使用して共済組合が指定する期日までに払い込んでください。
なお、ここで払込方法を変更することができますので、ご希望の方は共済組合にご連絡ください。
(4) 前納割引
掛金をまとめて前納した場合、年4.0%による複利原価法によって割引かれるため、掛金額が安くなります。
【掛金を前納した場合の計算式】 ※資格取得1年目の場合
| 1か月分の掛金額 × 前納倍率 |
| (小数点以下四捨五入) |
【前納月数と納入倍率】
| 前納月数 | 前納倍率 | 前納月数 | 前納倍率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.9967369 | 7 | 6.9092282 |
| 2 | 1.9902215 | 8 | 7.8834200 |
| 3 | 2.9804642 | 9 | 8.8544329 |
| 4 | 3.9674757 | 10 | 9.8222773 |
| 5 | 4.9512666 | 11 | 10.7869636 |
| 6 | 5.9318472 | 12 | 11.7485020 |
【前納できる期間について】
| ア) |
半年前納 前期:4月分~9月分(納付期限:3月末日) 後期:10月分~翌年3月分(納付期限:9月末日) |
|---|---|
| イ) |
一年前納 4月分~翌年3月分(納付期限:3月末日) |
| ウ) |
資格取得時の最初の払込時(半年前納・一年前納) 資格取得時の最初の払込時のみ、最初の1月分が「当月払い」の扱いとなるため割引されません。2月目以降については割引の対象となります。 |
(例) 4月1日に資格取得、半年前納する場合

(5) 資格喪失による前納掛金の還付について
掛金を前納された方が年度の途中で任意継続組合員の資格を喪失した場合は、ご本人の請求に基づき、前納された掛金のうち不要となった部分を還付します。
還付の請求書類については、資格喪失の申出をいただいたのち、共済組合から案内文書とともにご自宅へ送付します。
(例) 4月1日に資格取得し一年前納したが、10月25日に資格喪失した場合

